葦手、という不思議な言葉がある。植物である「葦」と、人の身体である「手」がひとつに結びついている。「手」は、かなを表す女手、漢字を表す男手のように、書体の意味。葦手は平安時代に書かれた、文字と絵の混成からなる独特の書体で、十世紀後半ごろから『宇津保物語』(国譲上)『新猿楽記』『源氏物語』(梅枝)などの文献に登場してくる。現存する葦手の作例は、いずれも十二世紀以降のものになり、「本願寺本三十六人家集」「葦手下絵和漢朗詠集」伝藤原公任筆「葦手歌切」などのほか、「平家納経」の一部にも葦手が使われている。
葦手の書体とは、どのような姿をしていたのだろうか。『源氏物語』には次のような一節がある。
葦手の冊子どもぞ、心ゝに、はかなうをかしき。宰相中将のは、水のいきほひ、ゆたかに書きなし、そゝけたる葦の生ひざまなど、難波の浦にかよひて、こなた、かなた、いきまじりて、いたう、すみたる所あり。又、いといかめしう、ひきかへて、文字やう石などのたゝずまひ、好み書き給へる枚もあり。 (『源氏物語』梅枝)
これをみると、冊子の中に「水のいきほひ」「そゝけたる葦の生ひざま」「文字やう石」などを葦手の書体で書いた、とある。

図1 「葦手歌切」
図版の「葦手歌切」では、「あ」の字が葦手で書かれており、文字の先端が葉のような形に変形している。これは「あさみどりいとよりかけて白露を たまにもぬけるはるのやなぎか」という歌の冒頭部分にあたる。ほっそりと柔らかな春の柳の葉が、白露を貫いて糸に通したように光らせている、そのしなやかな葉の形と生命力が、「あ」字の先端を芽吹かせてしまったかのようだ。
もうひとつの図版「葦手下絵和漢朗詠集」でも、文字の一部が葉、岩、水流の形に変形しているのがわかる。
葦手の書体で書かれたとき、文字は植物や水の流れに一体化するが、同時に、余白も自然の、水辺の空間とみなされるようになる。これは、紙を天地があり重力の働く空間と考える、東アジア漢字文化圏の書の形式に裏打ちされているのだろう。
よく言われることだが、中国や日本の書では、紙の余白は天地に広がる空間として認識されることが多く、西欧的な余白が発語の時間を表すのとは、基本的な性格を異にしている。また同じ漢字文化圏にあっても、金銀泥で植物などを描いた料紙に、文頭を上下させながら和歌を書く散らし書きなど、日本の書は自然景を背景とした空間性がとくにつよい。書道史家の古谷稔氏の言葉をかりるなら「わが王朝貴族たちは、みずから掌中の玉とした、”かな”および”和様漢字”に対して、単なる書だけの美的追求に満足することなく、料紙を大地に見立てるとすれば、そこに生い茂る水茎と空間との響き合う、音楽的美術的な感覚を、たえずとぎ澄ましていた」のである。
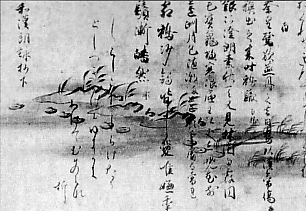
ところで、散らし書きが和歌と結びついていたように、葦手もまた、その用例から和歌を書きあらわす書体の一つであったと考えられている。前述の古谷氏は葦手の和歌について、「葦の生い茂る水辺に、水鳥や岩を配した景観の中に、文字を見え隠れさせて、一首を詠み込むというもので、歌と絵が同居していた」という。また、和歌の叙景の多くは実在の場所を詠んだものだが、美術史家の白畑よし氏は、葦手には歌の原となった実際の場所が絵の形で含まれているのだと述べている。
ふと疑問に思う。実在の水辺の空間を紙にうつし変えたかにみえる葦手を書くとき、その書き手はどこにいるのだろう。葦手や散らし書きを書くとき、手の運動は、空間を泳ぐ身体感覚の代わりをしているのではないだろうか。葦の葉と一体化してしまう文字、それは対象として眺められたものではなく、わたしには書いた人間の身体を感じさせる。身体が自然と同化してしまうということ。葦手は、これ以上行くともう言葉ではなくなるような、則をこえた所にあるのかもしれない。けれどそこには、自然と関係をもとうとする強い願いが感じられる。自然とどこかがつながっていて、半分その中に埋もれているような、人間の身体が見えてくる。口を閉ざす寸前の、眠りにおちる寸前の、もう余白へ、自然へ溶けてゆく自分。
*
自然とつながった身体、ということを考えてみると、それは和歌の中にも見いだされる。多田智満子氏は著書『魂の形について』の中で『万葉集』の歌をあげながら、日本に古くからみられる、魂を自然と結びつけようとする習慣にふれている。
磐代の浜松が枝をひきむすび 真幸くあればまたかへりみむ
君が齢も我が齢も知らむ磐代の岡の草根をいざ結びてな
前の歌は、謀叛の罪によって曳かれていった有間皇子が磐代の地を過ぎるとき、松の枝を結んで、ふたたび同じ松を生きて見られるようにと磐代の神に祈願した歌である。このような習慣は「結び松」といって、磐代の神に霊魂の一部を分け与えたことを意味するのだという。後の歌も、同じ磐代の神への祈願と契りとして草を結んだ歌である。どちらの歌も、結ぶという身振りによって、自然と自分を一体となし、そこに願いや祈りを通わせようとする行為が古くから行われていたことを示している。
このような和歌にみられる自然と身体の一体化について考えてみると、和歌に固有の書体であった葦手も、よく言われるような単なる飾り文字とは位相を異にする、もっと深い、存在にかかわる問題を含んでいるように思われる。このことを考えるために、十世紀から十一世紀初めの文献にのこる、なるべく古い、初源的と思われる葦手和歌の例をみてみたい。なかでも、ここにあげた二首の葦手和歌の例は、興味深い共通点をもっている。
底清くすむとも見えで行水の 袖にも目にもたえずもある哉
(『宇津保物語』国譲・上)
『宇津保物語』の歌は、書かれてはいない「わたし」の手と袖が、流れる水のなかに差し入れられて、冷たい水の感触とまじわる情景が浮かぶ。この歌は物語本文の中で、葦手を含む様々な書体の歌を並べた箇所にある。葦手以外の歌が、詠み手の身体に接していない「千鳥」や「飛ぶ鳥」「雲路」などを歌ったものであるのに対して、葦手の歌だけには水の中に差し入れられた詠み手の身体がある。また『栄花物語』の歌は、祝いの席で氷を扇形にしたものを硯の蓋に置いて献じた折り、その敷紙に書かれた歌とされている。ここでは、氷が時間を経ても溶けずに形を結んでいることと、献じた相手の栄えと長命とをかけている。
二首ともに文献に出てくる例であって、歌のどの部分がどのように葦手で書かれたのかを知るすべはない。しかし数少ない古い葦手和歌の例が、いずれも水にかかわるのみでなく、水や氷と人の身体・生命の一体化が主題となっていることは興味深い。葦手は、単なる装飾文字なのではなく、自然と身体、存在を一部で溶けあわせる役割をもっていたのではないだろうか。
ふたたび図版を見てみよう。葦の葉や水流と化した葦手の書体にみちびかれて、言葉は植物となって余白へ溶けようとし、余白に満ちる自然は紙面へと浮かびあがり、文字へと結晶しようとする。言葉の列は余白と交合しあっているかのようだ。ある部分は余白に埋まり、ある部分は余白から出てこようとしている。そこにあるのは、余白とからみあい、余白にまみれた身体、存在だ。この余白には深浅さえもある。それをときほぐしてゆくことで、紙面自体が出口にも入口にもなる、そんな自由が感じられる。
絵のような言葉、葦のような言葉、それは言葉の自立性という点では弱点でもある。だがそれでも、言葉が形と生成へと身をよじりあふれ出ようとするのはなぜだろう。
葦にとっては水辺の空間、水流にとっては川の広がりである、余白。その深みには、書き手の沈黙ではない、別の何ものかが眠っている。余白にはきっと、そのとき選ばれた言葉以外の世界すべてが潜んでいる。言葉の列にとっての他者、言葉が出会うべき対象である他者が 。豊穰なまでに余白に充満するもの、それは自然そのものであり、同時に神でもあり、また靄に包まれた、遠いだれかの気配―未分化な人称―であるのかもしれない。
*
葦手は和歌と深く結びついた書体であった。和歌を広く詩ととらえれば、葦手は詩に固有の書体であったといえる。
どんなに絵のような形をしていても、葦手は象形文字ではない。あくまで、どのように文字を書くかという「書体」である。つまり静的な結果の文字ではなく、動的な書くことそのもの、その身振りをも含んでいる。葦手はおそらく、書くことの欲望からうまれている、書くことに属した問題なのだ。
葦手の歴史を辿れば、十二世紀頃から徐々に蒔絵など工芸品装飾に使われるようになり、しだいに和歌の書体としては衰微してゆく。葦手が工芸品装飾としてしか使われなくなったことは、それが眺められるもの、読み解かれるものに限定されてしまったことを意味する。形としての静的な文字となり、書く、という身体を巻きこんだ運動の媒体ではなくなったということだ。このとき、詩の書体としての葦手は消滅する。
消えてしまった書体、葦手が、もし地下茎のようにその命脈を保っていたとしたら、そう考えてみる。はみだすこと、あふれること。余白と関係をもつこと。わたしたちの言葉はいま、葦手の欲望をどのように引きうけられるのだろうか。
参考文献
白畑よし「歌絵と葦手」『美術研究』一二五号、昭和十七年
小松茂美「葦手・上」『ミュージアム』一六九号、昭和四〇年
古谷稔編『日本の美術一八〇 平安時代の書』至文堂、昭和五六年
多田智満子『魂の形について』白水社、平成八年
『文字絵と絵文字』渋谷区立松濤美術館、平成八年
図版は次の文献より転載
石川九楊『書と文字は面白い』新潮社、平成八年
千野香織『10-13世紀の美術 王朝美の世界』(岩波日本美術の流れ 3)岩波書店、平成五年
home 明空 4号