黒い文字が火を吹くような言葉がほしい。
レンズが日光を集め白い紙を燃やすように、黒い文字のその場から。
燃え上がる紙から、言葉は、空気と交わるだろう。空気―わたしの居る世界そのものと、言葉が交わってほしい。護摩を焚き、呪文の文字を燃やして言葉の実現を祈るように、空気へ現実へと向けられた言葉。紙が燃やされることによって、言葉の血と空気の血が触れ合う、その場所が文字であるように。
紺色の紙に金色で経文を書した紺紙金泥経の存在は、暗黒のなかから顔を出す経文の光を暗示している。(石川九楊『筆蝕の構造』)
もし言葉が文字を燃やすことができるのだとしたら、発火をもたらす力は表現上の強さだけではなく、使われた言葉の歴史的な厚みと形象喩たる文字にも負っている。歴史的な言葉を、歴史の連続性の提示のためではなく、いま、現在の発火に向ける。紙の上にたえまなく供
給される酸素、目によって、そのまばたきによって、ひらかれ、剥かれる。そして言葉は太陽にまで見られたい。
わたしの、わたしが砂をどけてここに、紙面に晒した言葉を
太陽にまで見られたい。
わたしが太陽を見ているように。
太陽の視線に、わたしの言葉が影として映され、光のなかに黒い文字を浮かべて照らし返してほしい。
*
今年(注・1998年)6月に東京セントラル美術館で行われた、近代詩文書作家協会25周年記念「現代の詩歌と書の世界」展において、詩が、読まれたように書かれた作品に出会った。
長井清流書、川崎洋「鳥」原詩の行分けは
あの鳥であるが、あえて活字で並べて再現を試みれば、長井の書では
あの鳥がはばたけぱ
鳥より先に
空が飛び
あの鳥がくちばしを開けば
鳥より先に
世界が歌い出す
あの鳥
あの鳥があの鳥がはばたけぱ
鳥より 先に 空が 飛ぴ あの鳥が
くちばしを 開けば 鳥より 先に
世界が歌い出す あの鳥
というように並べかえられている。行間はきわめて狭く、行は互いに入り込み、水平方向への侵食作用、あるいは左行方向への解放運動がある。それは右下から左上に、行を通りぬけながら、空白へ向かってはばたいていく運動でもある。
最初の行の「あの鳥があの鳥がはばたけば」は、次の行の「鳥より」「先に」「空が」「飛び」「あの鳥」の5文字間の4つの空白を縫って、左行へ「はばたく」運動を手渡してゆく。そして前三行の内容に促され、「はばたき」と「くちぱし」の動きの重みを吸収して、最終行の「世界」がおもむろに歌い出す。
この書は、川崎洋の詩を変形しつつ、原詩がもつあざやかで生き生きとした運動性を表現しえている。軽やかな文字形とあいまって、紙面は朝の光を浴ぴているかのように動きに満ちてはばたいてゆこうとしている。
森本龍石書、吉田加南子「闇」の原詩は
闇
影がひらく
光
*
生まれようとしている
光の重さ
それが闇?
である。森本の書では基本的な行分けに変更はないが、アステリスクは取り去られ、さらに「生まれ」の下に、一行を半分にさいて「ようと」と「して」が並べて入れられている。
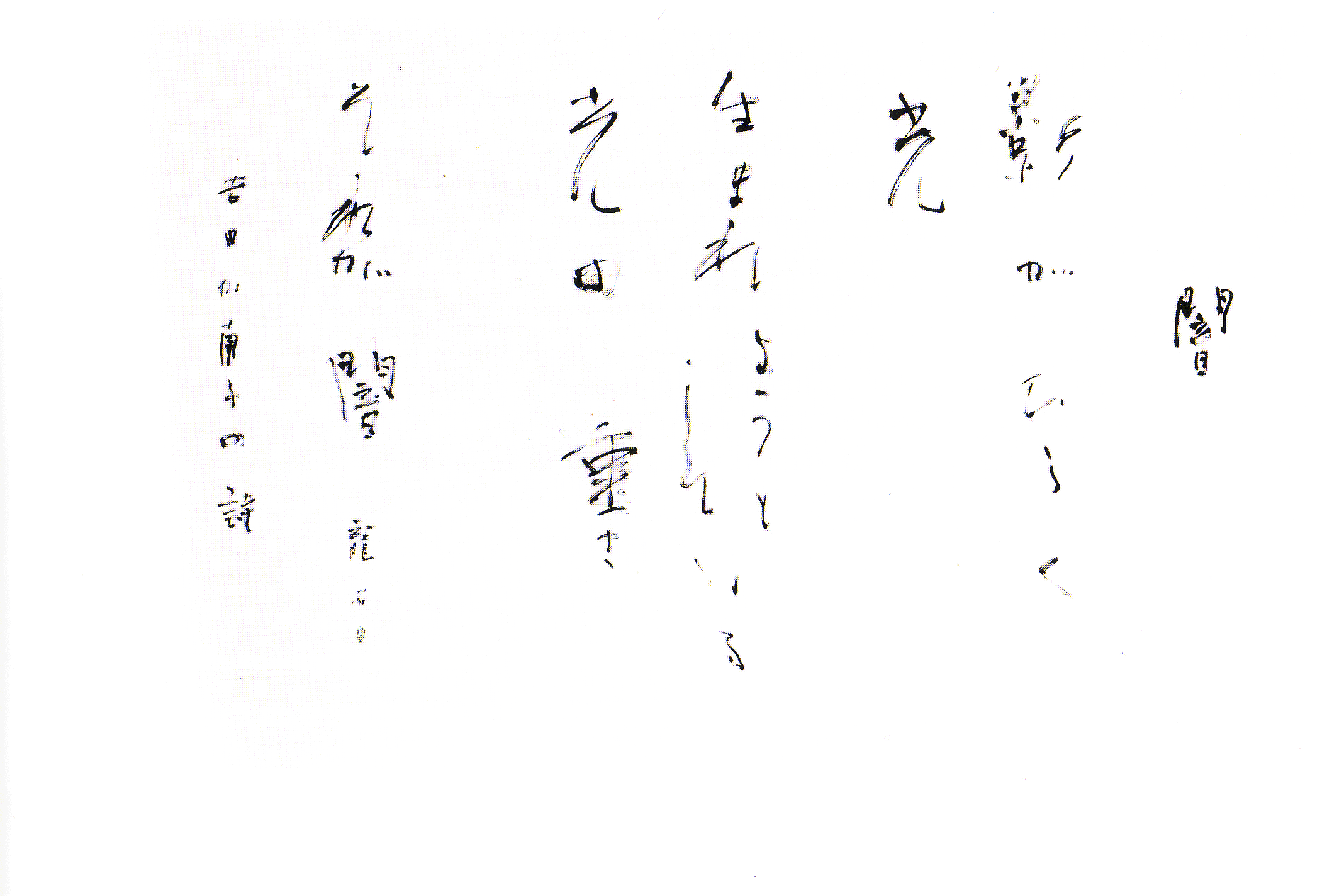
「影がひらく/光」の部分では、かすれながら運ばれた筆の痕跡によって「ひらく」運動が辿られる。「ひ」の生成、「ら」の佇まい、「く」の折れ曲がる運動によって、ゆっくりと時間をかけて、かすれによる痛みを湛えながら「ひら」いていく様子を見ることができる。そうして生じる「光」の字形は伸び伸びとしたものではなく、屈折した姿で、痛みを伴い、また上部の濃いところからかすれて伸ぴる下部が、影から生じてきた光であるようにも見える。
「生まれ」と「いる」の間にある「ようと」と「して」の二列の文字はやや外に膨らみ、いまだ胎内に蹲っているようである。よく見れば「ようと」は外に向かって張っているのに対して、「して」は「し」部がほとんど縦の波線のように下降し、屈折した「て」に重苦しくつながり、「して」の部分は「生まれ」ることをまだ逡巡しているかのようである。そのような、生まれいづることへの葛藤を背負った次行の「光」は、たっぷりとした空白をもって下部から「重さ」の言葉に強力に引っ張られている。まるで胚胎そのものの重みであるかのように。
この書においては原詩のもつ「ひらく」痛みとゆっくりとした運動性、光の「生まれようと」する「重さ」、その胚胎の感触と感情を伝えている。このような要素は吉田加南子の詩がもつ大きな特質とかさなるものだ。その意味でこの書はまさに「言葉の肉体、詩の裏側、裏側の詩」(石川九楊『ユリイカ』1998年・5月号)をなしていると言えるだろう。
これらの書は無論ひとつの解釈としてそこにある。しかし詩がなりたがっていた姿を見た、という思いはぬぐえない。詩の書き手は詩になにをしてやれるのだろうか。
詩を頁に、冊子にのせていく作業の途上、書として現前せられることをねがう詩、に直面せずにいられない。あるいは冊子のノドそれ自体を地上のクレバスととらえなおして受け入れるか。危険な誘惑であるのかもしれないが、なお書になりたがる詩の要求に耳を塞ぐことができない。
紙は書き手の遠方にある方を「天」、身近にある方を「地」とする。言葉が書かれたとした時、紙はいっきに天地に重カが負荷された対象世界と化し、現実とは異なるが、それに匹敵する表現世界を生むのである。(石川九楊「文字という虚構」)
紙に書いているのではない。紙を含む、その下の条件を含んだ机に対して書いている。それだけではない。(略)物理的に言えば、地球の中心に対して書いているのだとしか言いようがない。(略)紙と呼ばれているものは、作者と自然や世界との接触面、自然や世界との接触のために、磨き上げ、研ぎあげられた、自然や世界の一部、表皮なのだ。(石川九楊『筆蝕の構造』)
黒い文字が火を吹くような言葉がほしい。
文字のその場から、空気―この世界そのものと、言葉が交わるように。
詩がなりたがるものへ。
文字それ自体が呼ぶものへ。
参考資料
石川九楊『筆蝕の構造―書くことの現象学』筑摩書房、1992年
「現代の詩歌と書の世界」展図録、近代詩文書作家協会、東京セントラル美術館、1998年
『川崎洋詩集』現代詩文庫33、思潮社、1970年
吉田加南子『定本 闇』思潮社、1993年
吉増剛造・石川九楊対談「書と詩が互いに恋い焦がれ」『ユリイカ』1998年5月号
石川九楊「文字という虚構」『ユリイカ』1998年5月号