※小島郁子氏は、2006年11月現在「安藤郁子」に改姓しました。
小島郁子の作品の表面は、彼女の存在に敏感にはりめぐらされた皮膚のようだ。表面と空間は、そのまま作者の皮膚と、それを包む外界の気配として触覚的にあらわれてくる。小島作品の表面は「わたし」と「世界」とが出会い、浸透しあう境界、皮膜を思わせるものだ。
小島郁子は、一九七〇年青森県弘前市生まれ。岩手で大学生活を送り、大学院修了後に金沢の工房で陶芸家としての仕事を開始、九五年には「朝日現代クラフト展」グランプリを受賞した。近年はまた、青森に帰って制作活動をしている。
彼女の作品は陶の立体作品が中心で、三つのタイプに大別できる。一つは、「くもりの日」「月明かり」「きのうのいえ」など、家の形や車輪のような形から、羽状のアーチ形が伸びる連作。二つ目は橋や舟の形をした作品で、銅線の繊細な手すりがつくものもある。三つめは九九年にはじまる、「内側への入口」「降りていく水の中」「ひとりの」といった連作で、半球形の中央に穴があいていて、小さな階段によって見る者が内部へとみちびかれるような、量感のある作品群だ。

きのうのいえ 撮影:小島郁子
小島の作品は、つねに自分と外界の出会いの比喩としてあらわれてくる。彼女にとって制作は「自分の内側の空間にある小さな池」に「日々の様々な出来事が水面を波立たせる、その波立ちの様子を一つ一つ作品に置き換えていること」だという(注1)。作品は、淡い色の、かすれたような繊細な脆さのある表面を境界として、にじみあう内部と外部という空間によって成り立っている。小島は「羽のある作品では自分と外界が半々に関わっていて、半球形の作品は自分の内面に入っている感じがします」と語る。また近年青森に帰郷し、独立した一人の環境で創作していること、住環境の変化によって自分を取り巻く自然が変わってきたことも、内省的な作品の契機になっているという(注2)。
最近一年ほどのあいだに、彼女の作品は以前に比べて形が自由になってきた。これまで屋根や窓のある家の形をしていた部分が抽象的な立方体になり、はっきりした弧をえがいていた羽は、不定形な柔らかい形に変化してきている。小島によると、最近は羽の形を意図的に決めることをせず、土が垂れるままの形にしているのだという。そのためか、作品の境界から滲みだしてゆく感触は、さらに微妙な、広がりあるものとなってきた。
「小さな開放」は白っぽく乾いた質感の四角い形と、青みをおびた羽状の部分からなる。羽は、見えない何かをその上にのせて、延べさしだしている。作品の周囲には羽によって押しひろげられ、さしだされた何かを受けとろうとする空間がうまれている。
淡い青、茶、緑色の混ざりあう「どこかで」。ほそい羽は、何かをさししめすように空間へ延びる。その空間を明確に空ということはできない。もはや作品と周囲の空間は、家と空に限定されていないからだ。だからこそ作品は、幻めいた、見定めることのできない記憶をも誘ってくれる。
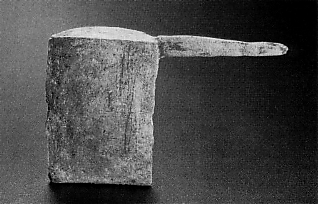
撮影:豊田洋司
半球形の作品群「内側への入口」「降りていく水の中」「ひとりの」では、外への動きはかなり抑えられているようだ。青い半球形の上面は、外界に滲みだしてゆくというよりは、あくまで膜として何かを内側に湛えている。
橋や舟の形をした作品ではどうだろう。橋は何かを渡しながら、あちらとこちらを区切るものであり、舟は水の中にあって、やはり、どこかへ何かを渡すイメージをもつ。淡紅色と青が混ざりあう、舟の形をした作品の周囲には、川霧や重みのある水のような、混沌として未分化な空気が漂う。
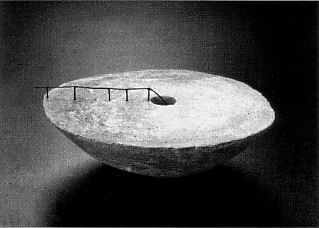
内側への入口 29.7W31.7H11.6cm
撮影:豊田洋司
淡い色合いの表面に、今ここにないはずの空間・時間を呼びよせる力は、小島郁子独特のものだ。「くもりの日」「月明かり」「きのうのいえ」の連作では、淡い青、あるいは灰色の表面が、いまここにはない「くもり」の外気、「月明かり」の光、「きのう」の時間を作品の周囲に呼びよせる。それら、ここにないはずのものと見る者は、しばしの間ひとところにいられる。表面のまわりに、きのうの空気がゆっくりと流れ、去っていったうゆうべの月の光があらわれる。この表面のそばにいると、そんなものが見える。
*
皮膜のうえでにじみあう内面と外界。しかしそれは措定されているものではないのではないだろうか。確定的な内部と外部ではないように思われる。
皮膚とはしかし、どのようなものだろう。
皮膚の中には外部受容器とよばれる神経があり、熱、冷たさ、接触、および痛みの感覚を中枢神経系に伝える(注3)。皮膚を通過した情報の堆積、記憶、それが皮膚の中で受容される。そのとき、皮膚もまた外へ与えられるのではないか。
風が皮膚を撫でてゆくとき、皮膚に風の感覚がのこされると同時に、風の中に皮膚の一部が奪われていったように感じること。皮膚の中に外部を受容する部分があり、外部が皮膚の中に入ってくる。そのとき同時に皮膚もまた外部の中にある。
「私は空間と時間とにぞくしているのであり、私の身体はそれらに貼りつき、それらを包摂している(注4)」
メルロ=ポンテイの言葉にならっていうなら、「わたしの皮膚」とは、同時に空間と時間の皮膜でもある。
感覚の損傷とは、ある領域の知覚器官が受容しなくなるのではなく、中枢への伝達が解体することであるという(注5)。皮膚は外部からの情報を受容し、中枢に伝える。だから距離がある、遠さがある。中枢からわすれられてしまった、果てのような皮膚。中枢は次の情報へずれていくのに、皮膚だけは、その感覚をかたくなに記憶しつづけるのだろうか。もう中枢から「わたし」からわすれられ、かえりみられなくなっても、記憶を溜めているのか。
そのような「わたし」から離れた場所にある皮膚。記憶を湛えてひとり揺れている皮膚。
「過去はあたかもわれわれの力が流出してゆく傷口のようなものとしてとどまる(注6)」
「わたしの身体は時間を湧出する(注7)」
呼びよせている。どこから。郷愁をさそう。ここにないものを思いだし、感じるよすが。そのための依り代となるもの、それが小島作品の皮膚なのではないか。
さらにその皮膚は、作者にとっての「何か」「どこか」「だれか」であるだけではなく、作品を見るわたしたちにも、そのからだを与えてくれる、依り代を与えてくれる。皮膜を使って、わたしたちもまた、ひとりひとりの固有のおもいでに、ひとりひとり別々の「きのう」に揺らめきでて、出会うことができる。夢を見ることができる。時間のなかに、ゆっくりと思いだすように立っている皮膚に、再び出会うことによって。
呼びよせている皮膚。見せられる、その皮膚が見ていたものを。時間のなかに立てられた皮膚。
*
陶芸と時間ということを考えてみるとき、そこには二種類の時間がありうるだろう。一つは、土が形づくられる時間、焼かれる時間などの制作プロセスの時間。二つめは素材に内在する時間である。
陶土や磁石といった素材に内在する時間とはどのようなものだろうか。小島によれば「土によってそれぞれ持っている時間が違ったり」するのだというが(注8)、土の持っている時間には、有機物として循環する時間と、鉱物として変化しない時間があるのではないか。 谷川渥氏は『形象と時間』の中で、西洋芸術のカテゴリーの一つである廃虚をとりあげ、こう論じる。「西洋の伝統的なヒエラルキー的世界観が、廃虚においてはまさしく方向を転じて『下降』の一途をたどる。(略)そしてその下降を惹起するものこそ『もっとも深い存在の層』を構成するところの『物質』、換言すれば『鉱物』にほかならないのである(注9)」。
過去の時間を喚起するという点において、西洋における廃虚にも似た享受のされ方をしてきたのが骨董だとすれば、骨董として陶器が伝えられてきた歴史性を、土という素材を通して、きわめて現代的なオブジェでありながら、小島の立体作品は担っているのかもしれない。
谷川氏はさらに、時間の最も根源的な表象が、対極間を振動することの連続であったことを指摘しながら、「振動する時間」の言語的痕跡を『古事記』に見出し、次のようにいう。少し長いが引用する。「『日』と『夜』とは、ここではまったく異質の時間として、交互に交替するものとして、すなわち非連続の連続として(略)「振動」としてとらえられているわけである。『日』と『夜』を一緒にして『一日』とする観念は、本来存在しなかったのだ」とするのだ。そして「まったく異質な時間である『日』と『夜』との交替するその境界の時間が、かつて柳田国男が『妖怪談義』(一九三〇年)において論じたように、『タソガレ』(誰そ彼)、『カハタレ」』(彼は誰)と呼ばれ、人顔の明瞭ならざるその刻限」であることを説く(注10)。
東北地方を訪れたことのある人なら、高く澄んだ空を淡く染める、印象的な夕暮れに出会ったことがあるだろう。小島郁子は、みずからが生まれ育った土地、東北の山の夕暮れを歩き、「陽が傾く頃の空気を作品にとりこみたい」と思う(注11)。奇しくも夕方とは、そのような「誰そ彼」の時間、だれなのかわからなくなる境界の時間だ。ここでもまた、わたしたちは、境目である、皮膜であることに出会う。
*
皮膜を通して得られる触覚は、あらゆる感覚のうちで、もっとも個人的に体験されるものであるという(注12)。だが、その触覚さえも、しだいしだいに「わたし」のものから、だれのものかわからないものへと移り変わってゆくのではないか。
「皮膚の或る一定の領域を一本の髪の毛で何度も繰り返して刺戟した場合、まず最初に得られるものは一対一対応の知覚であって、これははっきりと識別され、そのつど同一地点に位置づけられるものである。ところが刺戟が繰りかえされるにつれて、位置づけがより不明瞭なものとなり、知覚が空間中に拡がってゆき、同時に感覚は特殊的であることをやめる(注13)」さらに
「知覚は志向的であるけれども、そこには非人称化の芽が含まれている。(略)知覚は匿名であることを強いられるのだ(注14)」
「時間性において問題であるのは(略)他へ自分を開き、自分の外に出るすなわち、脱自的な仕方で存在するこの主体性である(注15)」
「脱自的」に、剥がれるように存在する時間。遠のいてゆく、離れてゆく「わたし」の皮膚。
小島作品の皮膚はそのような時間を、とてもやさしい表情で現わしている。
わたしが見ているとき、だれかがわたしの後ろから見ている。だれかが見ているから、その先にわたしが見ている。懐かしいやさしさに促されて、またある時は、「忘れてはならないこと」という小島の題名のような、名づけようのない約束に背中を押されて、わたしたちは見る。見ることを引き継ぐ。その先に、だれのものでもなくなった、わたしたちの皮膚が揺らめいている。
注1 「Jin Ceramic & Paper Session 礒﨑真理子・小島郁子・横田慧・石田智子4人展」パンフレット、ギャラリー人、1999年。
注2 1999年10月、筆者によるインタヴュー。
注3 エドワード・ホール著、日高敏隆・佐藤信行訳『かくれた次元』みすず書房、1970年、81頁。
注4 モーリス・メルロ=ポンティ著、竹内芳郎・小木貞孝訳『知覚の現象学Ⅰ」』みすず書房、1967年、236頁。
注5 前掲書メルロ=ポンティ、135頁。
注6 前掲書メルロ=ポンティ、152-153頁。
注7 末次弘『表現としての身体』春秋社、1999年、94頁。
注8 金子賢治「さぐりとる美しい形―小島郁子論」プラスマイナスギャラリー小島郁子展パンフレット、1997年。
注9 谷川渥『形象と時間』講談社学術文庫、1998年(白水社、1986年)。
注10 前掲書谷川、15-16頁。
注11 1998年6月の書簡より。
注12 前掲書ホール、92頁。
注13 前掲書メルロ=ポンティ、136頁。
注14 前掲書末次、91頁。
注15 前掲書末次、96頁。
home 明空 6号